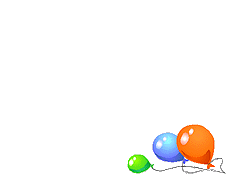気球観測機器の北京への輸送、北京中国科学院大気物理研究所で持ち込み荷物の点検、北京中国科学院大気物理研究所に残置してある福岡大学の受信装置類の点検、アンテナの仮組み立ての後OPCゾンデからの信号送信と受信システムの受信テスト終了。
放球に関しては、おおよそ100メートル毎分の上昇速度で浮力調整することとしました。X-Dayの想定は、5月6日午後と概定しておりますが、天気とにらみ合わせて現地部隊の判断が優先されます。
5日チンタオにて放球準備作業 福岡、金沢観測継続
6日放球 福岡、金沢観測継続
7日予備日 福岡、金沢観測継続
チンタオ現地時間午前8時ー9時(日本では、5月7日、午前9時ー10時になります)の時間に、
エアロゾルゾンデを放球しました。放球現地時間は1040、弱い東風(東向き?)で気球はほとんど真上に上がってゆく感じ。GPSは、調子悪かったが放球したら良くなった(おそらく、衛星の位置が悪く地上ではうまく計測できなかったが、上空に上がると水平線近くの衛星もしっかり見え始めたということと思います)。2006年、春季の気球観測実験と関連して、今日、チンタオで放球した、エアロゾルゾンデ観測は午後6時にて終了しました。(海に落ちました。)
チンタオから放球された気球は、当初の設定どおり90メートル毎分の低上昇速度で上昇し、国際プロジェクト対応のテーマの一つであった「大陸と海洋の境界上の接地境界層の構造」を比較的うまく観測したと思われます。
その後、強い高気圧の循環の中できわめてゆっくり移動し、チンタオの当方の沖合い150キロメートルあたりで対流圏を抜け出たと予想されます。その後も、気球はきわめてゆっくり東の方向へ移動しながら上昇し放球後約6時間後に30数キロメートルに達しバーストしたと考えられます。パラシュートで下降する際のわずかな時間西風に乗ったようで、信号が途絶えた地点は、チンタオからおおむね300km東に行ったところ(地上8キロ?)でした。風の予想が当たらず(当初は、対流圏上部まで達すれば、比較的強い西風に乗り半日程度で日本側の電波受信可能範囲に入ると単純に考えていた)、強い高気圧循環の影響下でふらふらする可能性を読みきれなかった点は、反省材料として今後に残りました。
第2の目論見であった「東シナ海、日本海横断飛行による、大陸起源空気の変質の解明」のすべてを実施することは、そんなわけで、出来ませんでしたが、変質の初期段階は抑えられていると予想しております。
8日撤収 北京へ移動 福岡、金沢観測終了
5月8日の石川工業高等専門学校での観測は、チンタオで気球を揚げたときの空気塊を観測することになりそうで興味深いものになりそうです。2006年、春季の気球観測実験と関連して、
昨日(5月8日)にて、係留気球観測を無事に終了しました。
合計3回行いました。(1回目:5月4日、2回目:5月6日、3回目:5月8日)
9日北京より帰国
観測参加機関およびグループ
金沢大学(自然計測応用研究センター、21COE、その他)、石川高専、熊本県立大学、福岡大学理学部、中国科学院大気物理研究所、チンタオ気象局、韓国気象局
観測連絡先(通知する)
気象研究所 酒井 哲、三上正男 そのほかADEC関係者、環境研究所 西川雅高、森 育子、富山高専 丁子哲治、富山環境科学センター 木戸瑞佳、三重大学 福山 薫、韓国気象庁アンミョンド観測所、韓国気象庁気象研究院、中国科学院安徽光学精密機械研究所(周 軍)、中国科学院寒区乾区環境与工程研究所(沈 志宝)、中国科学院気象研究院(張 小曳)、ADEOS関係者、ACE-Asia/ABC関係者
横断気球観測のイメージ
気球は、観測データを電波で地上に送りながら西風に乗って移動してゆく。一つの地上基地から気球を監視できるのは200kmから300kmなので、一つの受信局のみで電波を受けても洋上の様子を捉えきれない。多点で受信することが出来れば広い範囲の情報が得られる。




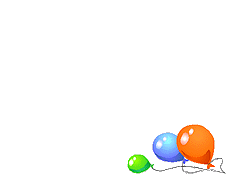 2006年春季 気球観測実施計画
2006年春季 気球観測実施計画